今日は、千葉県特別支援教育兼杞憂連盟言語障害教育研究部会秋期研修会で話しました。昨年も同じ研修会で話しています。そして、昨年と同様、今年もオンラインでした。コロナが始まって、何度も、オンラインで講演や講義をしていますが、どうも、慣れません。丸1日の講義で、1コマ90分の講義を4コマしたこともあります。受講者の方のほうがしんどいだろうと思いますが、話す僕も、聞き手の反応が分からないことが、何よりもしんどいです。
今日の研修会は、90分。たくさん資料を用意しました。話したいことは山ほどあるので、90分では到底話せません。後で、補ってもらおうと思って、たくさん用意しました。昨年とかぶらないようにと気をつけました。
今年の演題は、「どもる子どもが、幸せに生きるために」です。
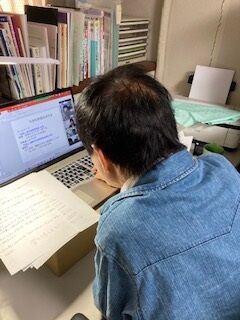 まず、人が幸せに生きるために必要なものから話を始めました。まず、空間・時間・仲間の三つを指す「三間」。これは、トーベ・ヤンソンのムーミンの話からヒントを得たものです。多くの人がムーミンの話をご存知なので、すっと入るようです。ことばの教室が、どもる子どもにとって、ムーミン谷であってほしいと思っています。
まず、人が幸せに生きるために必要なものから話を始めました。まず、空間・時間・仲間の三つを指す「三間」。これは、トーベ・ヤンソンのムーミンの話からヒントを得たものです。多くの人がムーミンの話をご存知なので、すっと入るようです。ことばの教室が、どもる子どもにとって、ムーミン谷であってほしいと思っています。
次に共同体感覚。これは、アドラー心理学の大切な3つの概念です。自己肯定・他者信頼・他者貢献、この3つの感覚を共同体感覚といいます。
そして、交流分析の中から、プラスのストローク。プラスのストロークには、言語的なもの、心理的なもの、身体的なものがあります。反対のマイナスのストロークについても触れました。無視が一番嫌なので、プラスのストロークが得られないなら、マイナスのストロークを得ようとするのは、よく理解できるようです。
どもる子どもはもちろん、担当者自身も、幸せに生きてほしいと思いながら、話していました。
基本的な吃音の基礎知識は、資料として配付しました。今日は、簡単に、吃音について、治療の歴史、治療がなぜ失敗するのか、それでも少しでも改善してあげたいと思う人たちのことなどに話を進め、吃音についてのまとめました。
吃音は、ひとりひとり違います。ひとりの中でも、ライフスタイルによって変わります。多様性と大きな変動性があるのです。その吃音について、吃音検査をして、把握しようとする人がいます。検査は、その後の処遇に結びついてこそ意味があるのですが、細かい検査をしても、対策としては、ゆっくり話すという訓練しかありません。意味のない検査ではなく、その子どもの吃音について、その子ども自身について、対話を通して、担当者と子ども自身が知ることが大切です。
吃音の影響には、大きな個人差があります。あまりどもっていないのに、とても悩んでいる人もいますし、ひどくどもっていても、豊かに自分らしく生きている人もいます。症状の改善を目指すことは、それほど大きな意味がないのです。
子どもが幸せに生きるために、吃音に大きく影響を受けず、自分らしく生きていくために、ことばの教室担当者として、何ができるだろうか。吃音をマイナスのもの、劣ったものと思わないような子どもになってほしい。どもる子どもをかわいそうな子だととらえてほしくないのです。吃音についてマイナスの物語を持っている子どもなら、その子と一緒に、吃音肯定の物語を作り替えていくことを、一緒にしていただきたい。それこそが、教育の場である、ことばの教室でこそできることです。教師は、子どもの同行者であっていただきたいと願います。
そのためには、担当者自身も、自己肯定感を持ってほしいと思います。自己肯定感を持つのは難しいのかもしれません。他者に敬意を示し、他者を大切に親切にすることから、自己肯定感が生まれます。これは、自分が嫌いで、自己肯定できなかった僕が、自己肯定の道筋に立てたのは、セルフヘルプグループで仲間を信頼し、大切して一緒に様々な活動を通して得られたものだからです。その活動を通して他者貢献感が持て、それで初めて、自己肯定ができるようになったという僕自身の経験によります。
共同体感覚のもつための三つ、他者信頼→他者貢献→自己肯定と進んでいったのが僕の歩んだ道でした。初めに、自己肯定感を高めることはから入ると難しいのですが、ことばの教室の担当者が、子どもとともに、自己肯定感を高めていくことができれば、すばらしいことだと思います。
最後に話したのは、半径3メートルの幸せです。自分の周りの人、顔を思い浮かべることのできる半径3メートルの人たちを大切にすることです。ちょっとしたことばをかけ、相手を尊重し、それらの人への愛を惜しまないこと、愛をケチらないことです。
話したいことがいっぱいあって、やっぱり、時間が足りませんでした。後半は、早口になってしまったかもしれません。
でも、こうして、自分の考えたこと、思っていることを伝える場があることは、僕にはとても幸せなことだと思いました。コロナが落ち着いて、対面でお会いし、やりとりをしながら、お話したいなあと思いながら、90分の話を終えました。このように機会を与えていただいたこと、感謝しています。
日本吃音臨床研究会 会長 伊藤伸二 2022/10/19
今日の研修会は、90分。たくさん資料を用意しました。話したいことは山ほどあるので、90分では到底話せません。後で、補ってもらおうと思って、たくさん用意しました。昨年とかぶらないようにと気をつけました。
今年の演題は、「どもる子どもが、幸せに生きるために」です。
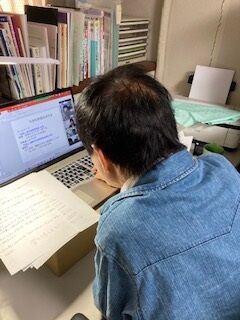 まず、人が幸せに生きるために必要なものから話を始めました。まず、空間・時間・仲間の三つを指す「三間」。これは、トーベ・ヤンソンのムーミンの話からヒントを得たものです。多くの人がムーミンの話をご存知なので、すっと入るようです。ことばの教室が、どもる子どもにとって、ムーミン谷であってほしいと思っています。
まず、人が幸せに生きるために必要なものから話を始めました。まず、空間・時間・仲間の三つを指す「三間」。これは、トーベ・ヤンソンのムーミンの話からヒントを得たものです。多くの人がムーミンの話をご存知なので、すっと入るようです。ことばの教室が、どもる子どもにとって、ムーミン谷であってほしいと思っています。次に共同体感覚。これは、アドラー心理学の大切な3つの概念です。自己肯定・他者信頼・他者貢献、この3つの感覚を共同体感覚といいます。
そして、交流分析の中から、プラスのストローク。プラスのストロークには、言語的なもの、心理的なもの、身体的なものがあります。反対のマイナスのストロークについても触れました。無視が一番嫌なので、プラスのストロークが得られないなら、マイナスのストロークを得ようとするのは、よく理解できるようです。
どもる子どもはもちろん、担当者自身も、幸せに生きてほしいと思いながら、話していました。
基本的な吃音の基礎知識は、資料として配付しました。今日は、簡単に、吃音について、治療の歴史、治療がなぜ失敗するのか、それでも少しでも改善してあげたいと思う人たちのことなどに話を進め、吃音についてのまとめました。
吃音は、ひとりひとり違います。ひとりの中でも、ライフスタイルによって変わります。多様性と大きな変動性があるのです。その吃音について、吃音検査をして、把握しようとする人がいます。検査は、その後の処遇に結びついてこそ意味があるのですが、細かい検査をしても、対策としては、ゆっくり話すという訓練しかありません。意味のない検査ではなく、その子どもの吃音について、その子ども自身について、対話を通して、担当者と子ども自身が知ることが大切です。
吃音の影響には、大きな個人差があります。あまりどもっていないのに、とても悩んでいる人もいますし、ひどくどもっていても、豊かに自分らしく生きている人もいます。症状の改善を目指すことは、それほど大きな意味がないのです。
子どもが幸せに生きるために、吃音に大きく影響を受けず、自分らしく生きていくために、ことばの教室担当者として、何ができるだろうか。吃音をマイナスのもの、劣ったものと思わないような子どもになってほしい。どもる子どもをかわいそうな子だととらえてほしくないのです。吃音についてマイナスの物語を持っている子どもなら、その子と一緒に、吃音肯定の物語を作り替えていくことを、一緒にしていただきたい。それこそが、教育の場である、ことばの教室でこそできることです。教師は、子どもの同行者であっていただきたいと願います。
そのためには、担当者自身も、自己肯定感を持ってほしいと思います。自己肯定感を持つのは難しいのかもしれません。他者に敬意を示し、他者を大切に親切にすることから、自己肯定感が生まれます。これは、自分が嫌いで、自己肯定できなかった僕が、自己肯定の道筋に立てたのは、セルフヘルプグループで仲間を信頼し、大切して一緒に様々な活動を通して得られたものだからです。その活動を通して他者貢献感が持て、それで初めて、自己肯定ができるようになったという僕自身の経験によります。
共同体感覚のもつための三つ、他者信頼→他者貢献→自己肯定と進んでいったのが僕の歩んだ道でした。初めに、自己肯定感を高めることはから入ると難しいのですが、ことばの教室の担当者が、子どもとともに、自己肯定感を高めていくことができれば、すばらしいことだと思います。
最後に話したのは、半径3メートルの幸せです。自分の周りの人、顔を思い浮かべることのできる半径3メートルの人たちを大切にすることです。ちょっとしたことばをかけ、相手を尊重し、それらの人への愛を惜しまないこと、愛をケチらないことです。
話したいことがいっぱいあって、やっぱり、時間が足りませんでした。後半は、早口になってしまったかもしれません。
でも、こうして、自分の考えたこと、思っていることを伝える場があることは、僕にはとても幸せなことだと思いました。コロナが落ち着いて、対面でお会いし、やりとりをしながら、お話したいなあと思いながら、90分の話を終えました。このように機会を与えていただいたこと、感謝しています。
日本吃音臨床研究会 会長 伊藤伸二 2022/10/19