『治したくない−ひがし町診療所の日々』(斉藤道雄著 みすず書房)関連(7)
斉藤道雄さんが送って下さった『治したくない−ひがし町診療所の日々』を出発に、斉藤さんとの出会い、川村敏明さんという精神科医のこと、べてるの家のことなど、話が広がりました。今回で一応の区切りと考え、『吃音の当事者研究−どもる人たちが「べてるの家」と出会った』(金子書房、向谷地生良・伊藤伸二)の本に、斉藤道雄さんが、寄せて下さった文章を紹介します。
向谷地生良さんのことは、以前ブログに書きました。島根県の浜田市のレストランでばったり出会うなど、不思議な出会いがあるのですが、最初の出会いは斉藤さんが作ってくれました。
北海道浦河の「べてる祭り」に、長年つきあいのある統合失調症の青年のお母さんと参加した時です。「浦河に来られるのなら、浦河にある私の自宅で身近な人たちと食事会をするので、いらっしゃいませんか」と斉藤さんが誘ってくれました。喜んでお母さんとお伺いしたのですが、斉藤さんとおつきあいのあるいろんな方が招待されていた中に、向谷地さんのご家族がおられました。以前から向谷地さんに私たちの2泊3日の吃音ショートコースの講師として来ていただきたいと考えていたので、またとない機会だと、斉藤さんに紹介していただき、話をしました。そして、当時としては珍しい3日間の向谷地さんのワークショップが実現したのです。楽しく、有意義だった吃音ショートコースの最終日、興奮気味に向谷地さんが、「このワークショップの記録を本にしましょう」と言って下さり、実現した本が、『吃音の当事者研究−どもる人たちが「べてるの家」と出会った』(金子書房、向谷地生良・伊藤伸二)です。
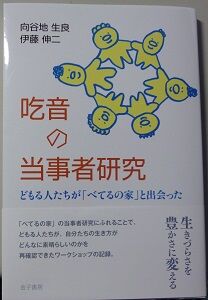 この本のまえがきに、斉藤さんが書いて下さった文章。ここに、僕たちのことを本当に理解して下さる方がいると心から実感できた文章でした。今、読み直してみても、その思いは全く変わりません。出会いと、その後のおつき合いに、感謝します。
この本のまえがきに、斉藤さんが書いて下さった文章。ここに、僕たちのことを本当に理解して下さる方がいると心から実感できた文章でした。今、読み直してみても、その思いは全く変わりません。出会いと、その後のおつき合いに、感謝します。
日本吃音臨床研究会 会長 伊藤伸二 2020/5/29
斉藤道雄さんが送って下さった『治したくない−ひがし町診療所の日々』を出発に、斉藤さんとの出会い、川村敏明さんという精神科医のこと、べてるの家のことなど、話が広がりました。今回で一応の区切りと考え、『吃音の当事者研究−どもる人たちが「べてるの家」と出会った』(金子書房、向谷地生良・伊藤伸二)の本に、斉藤道雄さんが、寄せて下さった文章を紹介します。
向谷地生良さんのことは、以前ブログに書きました。島根県の浜田市のレストランでばったり出会うなど、不思議な出会いがあるのですが、最初の出会いは斉藤さんが作ってくれました。
北海道浦河の「べてる祭り」に、長年つきあいのある統合失調症の青年のお母さんと参加した時です。「浦河に来られるのなら、浦河にある私の自宅で身近な人たちと食事会をするので、いらっしゃいませんか」と斉藤さんが誘ってくれました。喜んでお母さんとお伺いしたのですが、斉藤さんとおつきあいのあるいろんな方が招待されていた中に、向谷地さんのご家族がおられました。以前から向谷地さんに私たちの2泊3日の吃音ショートコースの講師として来ていただきたいと考えていたので、またとない機会だと、斉藤さんに紹介していただき、話をしました。そして、当時としては珍しい3日間の向谷地さんのワークショップが実現したのです。楽しく、有意義だった吃音ショートコースの最終日、興奮気味に向谷地さんが、「このワークショップの記録を本にしましょう」と言って下さり、実現した本が、『吃音の当事者研究−どもる人たちが「べてるの家」と出会った』(金子書房、向谷地生良・伊藤伸二)です。
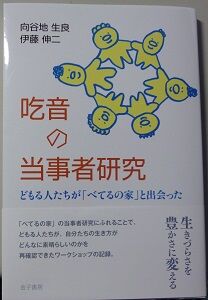 この本のまえがきに、斉藤さんが書いて下さった文章。ここに、僕たちのことを本当に理解して下さる方がいると心から実感できた文章でした。今、読み直してみても、その思いは全く変わりません。出会いと、その後のおつき合いに、感謝します。
この本のまえがきに、斉藤さんが書いて下さった文章。ここに、僕たちのことを本当に理解して下さる方がいると心から実感できた文章でした。今、読み直してみても、その思いは全く変わりません。出会いと、その後のおつき合いに、感謝します。「吃音の当事者研究」に寄せて
斉藤道雄(さいとうみちお・ジャーナリスト)
「治るかどうかではない、どう生きるかが問題なのだ」
この言い方には、深いなじみがある。
伊藤伸二さんにはじめて会ったとき、ああ、この人はぼくの出会った多くの人たちとおなじことばをしゃべっていると思った。
吃音は治らない、治さない、仲よくしていまを生きる。
この「吃音」を「精神病」と言い換えれば、それはそのまま北海道浦河町の精神障害者グループ、べてるの家の人びとの言い方になる。吃音と精神病はまったくちがうものだといわれそうだが、どちらも、治らない、治しても再発をくり返すし、多くの人は一生をそれとともに生きていかなければならない、ということでは共通している。治らない、治しがたいにもかかわらず、人は「治すこと」にとらわれ、そこから抜け出すためには自分自身を拠り所とする知恵と仲間の存在が欠かせない、そういった点でも、吃音と精神病はおどろくほど似かよっている。
考え方、価値観がおなじ地平にある吃音の伊藤さんとべてるの家の人びとは、言語までもが共通している。治すのではない、自分自身を生きるのだという言い方、来るかどうかわからない明日のしあわせより、今日の、今のしあわせをたいせつにするということ。どんなに離れていても、いっぺんも出会ったことがなくてもおなじことばがぼくらはどこかでつながっているという安心感、既視感をもたらしてくれる。
その一方で、ぼくは大多数の人びとがしゃべる別のことばも知っている。
治そう、治さなければいけない、治そうとしないのは敗北だ。そう語る人びとは、あなたはそのままでいてはいけない、変わらなければいけないという。しかもそれはどうやら無条件に、みんなとおなじになること、多数派とおなじ人間になって多数派とおなじ人生を歩むことを前提としている。
彼らは、みんなとおなじになうるというだけではない。いまよりさらに大きく、強くなろう、病気や障害だけでなく自分の弱さや迷いを克服し、さらなる高みをめざそうという。それがあなたのあるべき姿なのだと。そうした別のことばは、ぼくらが生まれてからこのかたずっと変わることなく学校で、会社で、社会で、テレビや新聞で、あらゆるすき間を埋めてぼくらに投げかけられてきた。治そうということばを聞いているとき、ぼくらはこの社会のまぎれもない多数派だった。
治さないという少数派のことばと、治すべきだという多数派のことばは、まったくちがう別のことばなのだと思う。
そのちがいは、自分のことばと他人のことばのちがいからきている。
伊藤伸二さんと彼の仲間は、自分のことばをしゃべっている。吃音を治すべきだという多数派の人びとは、他人のことばをしゃべっている。ぼくにはそう思えてならない。
自分のことばは、自分の抱えた苦労や困難を真剣に悩んだ人びとが、その悩みのなかで自分自身が感じ考えたことを、自分のことばで語ろうとする。けれど他人のことばをしゃべる人びとは、自分の困難について自分で考えることをやめ、人に説明してもらい、人に語ってもらう。あるいは人がしゃべったこと、とくに権威や専門家といわれる人びとのことばをそのままわがものとしてしゃべっている。自分のことをいっているようでも、また自分のことばだと思っていても、それはほとんどいつも他人のことばの受け売りだ。ときには権威や専門家といわれる人びとですら、そのいっていることは他人の受け売りにすぎない。
もちろん、自分のことばと他人のことばは画然と分けられるものでない。ぼくらはいつだって他人に影響され、他人との会話のなかで自分の考えをまとめているし、まったく自分ひとりでことばを見いだす人なんていない。どんなに受け売りの上手な人でも、いくばくかの独自性はあるだろう。けれど二つのことば、自分のことばと他人のことばのちがいは、本人がほんとうに悩んだか、ただ迷っただけかのちがいからはじまっている。
吃音であれ精神病であれ、治すか治さないか、あるいは治せない自分はそんな自分の人生をどう生きるかは、自分で考え、最後まで自分で考えなければならないこととしてある。周囲がなにをいっても、どんなことをいわれても、また専門家がどう説明してくれても、それが自分自身の問題として投げかけられている以上、自分ひとりで引き受けなければならない。少なくともべてるの家の人びとは、三十年に及ぶ当事者活動で無数の失敗を重ねながら、そのことをくり返し学んできた。アルコール依存や統合失調症をはじめとする精神病は、自分自身のことばで語りださないかぎり出口を見いだせない。それは彼らが命がけで見いだした、病気を生きる手段であり、知恵であり、ついには目的でもあった。
自分のことばで、自分自身を語るということ。それがどれほどたいせつなことかを、そしてときにはそれこそが生きることの意味なのだということを、べてるの家の人びとはいつでも語ってくれるだろう。それは決してひとりではできない作業だということも。そのために仲間がいて、仲間とともに進める当事者研究というしくみがあるのだということも。
自分のことを、自分のことばで語る。それがはじまったときに、当事者研究ははじまっている。だとするなら、伊藤さんたちの当事者研究はべてるの家と出会うずっと前からはじまっていた。伊藤さんがべてるの家の向谷地生良さんと出会うことで、二つの当事者研究が交差し、それぞれの当事者の悩みはさらに深められることになった。吃音者が、精神病者が、自分の苦労と悩みを自分のことばで語り継ぐとき、ぼくはそのことばを彼らの名前とともに記録しつづける。それこそがぼくにとって理解可能なことばであり、伝えるべき価値をもつことばだからだ。
日本吃音臨床研究会 会長 伊藤伸二 2020/5/29