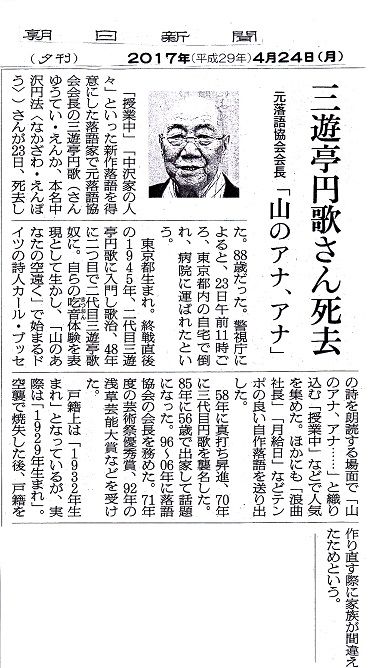
吃音(どもり)を笑いに生かした落語家・三遊亭円歌さん
「山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う」
カール・ブッセの詩を、「山のアナ、アナ、アナ、アナタ、もう寝ましょうよ」と、子どもが朗読する場面。当時、大人気だった三遊亭歌奴さんの落語が、ラジオやテレビから流れてくるのが、吃音に深く悩んでいた21歳の夏まではとても嫌でした。
1965年夏、吃音をどうしても治そうと、1か月、東京正生学院の寮に入り、朝から夜遅くまで吃音治療に励みましたが、僕だけでなく、当時来ていた300人ほどの全員が治りませんでした。「どもりが治らなくては僕の人生はない」とあれだけ思い詰めていたのに、この1か月の吃音治療体験で、僕は吃音を治すことをあきらめることができました。
多くの人が、なかなかあきらめられずに、何度も東京正生学院を訪れたり、他の治療所を転々とするのに、なぜ、僕が1か月の一度きりの治療の失敗であきらめることができたのか、ずっと考えているのですが、いまだに完全に納得できる答えをもっていません。
1965年秋、どもる人のセルフヘルプグループ「言友会」を創立するころには、吃音については、まったくと言っていいほど悩まなくも、困らなくもなりました。吃音を認めた僕が聞いた歌奴さんの落語は、とでもおもしろく、自分自身が吃音に本当に悩んできた人だからこその優しさがありました。テレビやラジオからこの落語が流れる度に、いやな気持ちになってすぐにスイッチを切っていたのに、わずか2〜3か月後には、その落語を楽しんでいる、この変化は大きなものでした。
僕は、好きになったのですが、言友会の人たちの中には、吃音を笑いものにしていると、抗議したいという人も現れました。週刊誌『サンデー毎日』の編集部の仲介で、歌奴さんと会って話す機会をもつことができました。
その時、自分自身が国鉄の駅員で「新大久保」の名前が言えなかったこと、それで国鉄を辞めて、落語家になったことなどを話して下さいました。落語家になりたいと三遊亭円歌の門をたたいたとき、「私のような、どもりでも落語家になれるでしょうか?」と尋ねたら、師匠が「おおおおおお俺も、どもりだ」と言ってくれて、入門した話などは、とてもおもしろいものでした。人一倍どもりに悩んできたので、決してどもりを笑いものにしようとしているのではないと、丁寧に話して下さったことはよく覚えています。
その出会いを『サンデー毎日』が「愉快に仲間」だったかのコーナーで、記事として紹介してくれました。その記事がいつかなくなってしまったのは、とても残念です。
僕は落語が大好きなので、東京へ行ったときには、鈴本演芸場によく行きますが、確か、最近まで出演しておられたのではないかと思います。その看板を見る度に懐かしく思い出していました。お元気だったので、いつか話しかけたいと思っていたのですが、亡くなられ、それはかなわなくなりました。話しかければ、僕たちのことは思い出して下さっただろうと思います。ご冥福を祈りつつ、新聞記事と、僕たちの機関紙「スタタリング・ナウ」で紹介した記事を紹介します。

ビデオテープ 三遊亭円歌(落語家)
(僕は)吃音(きつおん)者ですからね。つまり駅員をやってても「新大久保」というのがいえなかったり、お客に道を聞かれてもなかなかすぐ答えられなかったり。……そういうことで自分にすごくプレッシャーかかってましたから。もしも何かでこういうことが治ることがねえかなあと。
終戦の前に上野の鈴本ヘフラッと入ったんですね。空襲が来たり警戒警報が出てる最中に、みんな防空ずきんかぶって、客席で笑ってるやつがいるんですよね。……その時にほんのちょぴっと明かりが見えたわけだよ、人の笑い声聞いてね。それで……オレの職業、これしかねえなあと思った。
師匠(先代・円歌も吃音者だった)が後年、私にゆってくれましたですけどねえ「お前の気持ち一番わかったのはオレじゃねえかなあ」と。
(新・テレビ私の履歴書 下町のイキな笑いが僕の人生 東京、16日から)
三遊亭円歌師匠の落語に学ぶ
宮島哲夫(新潟県長岡市)
三遊亭円歌師匠の寄席が長岡で行われました。今回はチャリティのこともあって、車椅子の障害者の方も大勢で、それらの方々への思いやりのこともあったのか、自らの吃音体験を交えた落語を語り、時間延長も構わない熱演ぶりでした。
私も以前から、師匠は吃音を治したい一念で落語界に入ったことなど、新聞記事で読んでいましたので、是非聞いてみたいと思っていました。
吃音談義は、さすがに落語協会会長の貫録十分、爆笑の連続、私にとっては笑うどころか、身を乗り出して聞いていました。私のようにいつまでも吃音にこだわり続けている者にとっては、説教のように身に染みる思いでした。
国鉄の駅員時代、「新大久保」というのが言えなかったり、小学校時代から、軍隊生活での吃音が原因で殴られたこと、どもりで苦労したことをうまく話のタネにできるのは、天性の落語が身についているからでしょうか。
終戦の前に、上野の鈴本に入り、人の笑い声を聞いて、オレの職業、これしかないと思ったこと、先代円歌師匠も吃音者だったことで、後年に、先代が「お前の気持ちを一番分かるのは、オレじゃねえかな」と語ったそうです。
私の隣には重度らしい視覚障害の若い女性が、さもおかしそうな様子で声を出して笑っていましたが、私は終わりまで心から笑うことができませんでした。吃音者である私は、話が身につまされたということだけでなく、寝たきりの妻の看護に明け暮れ、笑う余裕がなくなっていることに気づかされました。生活の中の笑いの大切さを改めて思いました。
帰りには、車椅子の友人に会って、師匠の人となりを語り、送迎車まで送りました。
「スタタリング・ナウ」 1996.8.15 NO.24より
日本吃音臨床研究会 伊藤伸二 2017/04/24